Last Updated on 3か月 by aisotota
まず結論:リレーは「電磁石で動くスイッチ」
リレーは 弱い電気で、強い電気をON/OFFする道具です。
内部は “コイル” と “接点” の2階建て構造になっています。
▽構造のイメージ図
┌──────── リレー本体 ────────┐
│ (コイル) ⇒ (接点が動く) │
│ 弱い電気 強い電気 │
└────────────────────┘
- コイル:指令側
- 接点:結果側(A接点 / B接点が並ぶ)
A接点とB接点は「コイルOFF状態」が基準
回路図や盤図は全て
コイルに電気が入っていない状態で描かれます。
▽基準状態の図
コイルOFF(電気なし)
A接点:開いている(OFF)
B接点:閉じている(ON)
コイルに電気を流すと「AとBは逆に動く」
▽動作図
コイルOFF → ONになる瞬間
A接点:開 → 閉
B接点:閉 → 開
完全に逆動作
この “逆に動く” が理解のキモ。
もっと視覚的に見る:動作アニメ風図
【コイルOFF】
コイル:OFF
A接点: [ | | ] ←開いてる
B接点: [―||―] ←閉じてる(電気流れる)
【コイルON】
コイル:ON
A接点: [―||―] ←閉じた(電気流れる)
B接点: [ | | ] ←開いた(電気切れる)
AとBは トグルスイッチの裏表みたいな動き。
リレーは “接点の数” が命
型番を見ると「2a1b」みたいに数字とアルファベットがある。
意味はこれだけ:
| 表記 | 意味 |
|---|---|
| 2a | A接点が2個 |
| 1b | B接点が1個 |
つまり1台のリレー内部に
複数のA接点+B接点がセットで入る。
リレーを経由する理由
- スイッチやセンサーは「弱い電気」しか扱えない
- モーター・照明は「大きい電気」が必要
→だから中間にリレーを必ず挟む。
[弱い電気のセンサー] → リレー → [強い電気の負荷]
センサーが直接AC200VをON/OFFできるわけじゃない。
ここまで理解したら “次は主回路” に入る
A接点 / B接点
+リレーの仕組みを理解した
→次は「マグネットスイッチとサーマルリレー」で
主回路を理解すると制御盤の全体図が読める人になる。
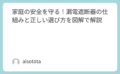
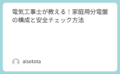



コメント